![]()
![]()
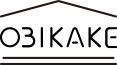
![]()
![]()
Be-dan
2019.9.9
自由で飾らない雰囲気のギャラリー「Diginner Gallery Workshop(ディギナー ギャラリー ワークショップ)」を運営する鈴木宏信さん。第1回ではギャラリーについて詳しく教えていただきました。
今回は、鈴木さんがギャラリーを始めようと思った理由、また仕事のやりがいについて、お話をうかがいました。

―鈴木さんが、ギャラリーを始めようと思ったキッカケは?
キッカケは、僕がニューヨークに住んでいたことが一番ですね。1990年代、画家を目指して、ニューヨークのブルックリンに住んでいました。当時のブルックリンには、僕と同じような若手アーティストがたくさんいました。
僕がたまたま住んでいたアパートの斜向いに、中堅アーティストの友人が住んでいて、そこのアパートによく若手アーティストが溜まっていたんです。そのうちに、その友人の自宅を「ギャラリー」代わりにして、週替わりでさまざまなテーマの企画を立てて、展示・キュレーションするようになったことが、キッカケですね。
―住居をギャラリー代わりに。じゃあ、お客さんもその中堅アーティストのファンだったのでしょうか?
いやいや。客引きも自分たちでやったんですよ。ギャラリーの主な宣伝場所は、クラブでしたね。僕らは毎晩、人が集まるところに行っては、白黒コピー機で刷った手作りのフライヤーを置いていました。あとはパーティーにいる人に直接、「週末、作品を展示するから」って言って渡すんです。
クラブ遊びをしている人たちって、その日のうちにパーティーを何件もハシゴするんですよ。だから、フライヤー1枚でもものすごい効果があって…。きっと行く先々で、「おもしろいのがやるぞ」って仲間に見せてくれるんだと思います。その流れでいろんな人たちに作品を見てもらえて、作品を買ってもらうこともありました。
自由な雰囲気の中で、自分たちの作品を発表するハブのような「場」を作り出したからこそ、僕も含めて若いアーティストの卵たちが活動することができたと思うんです。
―なるほど! その後もアメリカでアーティストとして活動を続けたのですか?
ビザの関係で日本に帰国し、活動を継続していましたが…。日本はアメリカと勝手が違っていました。

展示会を企画しても、日本には形式張ったギャラリーしか存在していなかったんですよね。ギャラリーというよりは、ホワイトキューブ(*)というイメージですよね。ギャラリーとして成立してしまった作品を置くハコみたいな。
*ホワイトキューブ:「白い立方体」。1989年に開館したニューヨーク近代美術館が導入し、展示空間の代名詞として用いられる言葉。
NYで体験した、気軽に展示できる自由な雰囲気の場所って、日本には全然なかったんです。唯一NYに似たような雰囲気といえば、カフェやレストランくらいでした。けど、そこは飲食店ですからね。飾る作品が、限られているじゃないですか。中途半端だなあ、窮屈だなあって思っちゃって。
そういう日本のギャラリー事情を肌身で感じて思ったのは、「若手アーティストにとって、世に出るまでの発表場所が少ないな」ということでした。こういう問題意識から僕は、「発表場所がないんだったら、NYの経験を活かして、自分でギャラリーを立ち上げてみるのも面白いな」と、考えました。それが2003年から2005年くらいです。
―その思いが、「Diginner Gallery Workshop」オープンにつながったんですね。でも、なぜ銀座や日本橋といったギャラリー中心地ではなく、自由が丘に作ったのですか?
NYのギャラリーみたいに自由な雰囲気を持つスタイルをゼロからやるには、銀座や丸の内エリアでは難しかったんです。単純に賃貸料が高いというのもあるのですが、銀座などの中心地では、一種の「バビロン」とも言うべき画廊やコレクターの濃密な社会がすでに出来上がってしまっていて。その中に何の実績もなく入っていって、いきなりポンと始めるのは、かなり厳しいのでは? と考えていました。
もともと政治嫌いなので(笑)、難しい気遣いとかがイヤだったんです。どうせ1人でやるし、何もない環境がいいなと思って探していたところ、縁があってここに巡り合いました。また、自由が丘には既存のギャラリーがほとんどなくて、「ああ、ここなら自由にやれるかな」と思えたんです。
―来年は開廊10周年を迎えますよね。これまで数多くの展示を手掛けられてきたかと思いますが、ギャラリー運営のやりがいって、どんなところにありますか?

自然光を利用した展示。入り口から見える作品は、思わず足を止めて見てしまいます。
自分の好きな作品に毎日触れられることですね。自分の見つけてきた作品に興味を持ってギャラリーに来てくれる人たちと、じっくり話をして「想い」を共有できるというのは、やりがいにつながります。
日本では美術館や博物館に行っても、カジュアルに話し込んだりとかできないでしょう。監視員が飛んできてすぐに「静かに」って言われますし。もちろん、他の鑑賞者の迷惑になるってわかっているんですけど、その場で作品の感想とか言いたい時があるじゃないですか。そういうところ、うちを含むギャラリーは寛大だと思います。
うちは、「居酒屋のような」飾らない雰囲気でやっています。だから「飲み屋か!ここは」という感じで、ざっくばらんに話すのもOKですよ。僕もたまに、お客さんとよく話し込んだりしますから。カジュアルに自然体で運営しています。
―本当に居心地がいいですね。意外にもスーツ姿のかたが、よく入っていますよね?
このエリアの特徴ですかね。隣が居酒屋なので、そのついでにフラッと覗いてくれるんでしょうね。

この前も閉店前に仕事帰りのサラリーマンが寄ってくれました。もちろん新規のお客さんも大事ですが、支えてもらっているのは、うちのことをすごくひいきにしてくれているコレクターさんですね。あとは自由が丘近辺の奥沢とか、近隣に引っ越してくる人たちも。うちで初めてアート作品を買いましたというお客さんが、結構多いです。
20代の頃から夢見ていた空間が、自分の手の中にある。今は一番、ギャラリーの経営が楽しいです!(第3回に続く)
information
Digunner Gallery Workshop
カザマナオミ個展 ハミダシタシュー
2019.09.06〜2019.09.16
展覧会詳細:https://obikake.com/exhibition/750-2/
公式サイト:http://diginner.com
★他のインタビュー記事を読む
國學院大學博物館広報・佐々木理良さん
山種美術館館長・山﨑妙子さん
その他の記事はコチラ
Writer | 齋藤 久嗣
脱サラして満3年が経過。現在は主夫業とアート系のブロガー&ライターとして活動中。
首都圏を中心にほぼ毎日どこかの展覧会に出没中。日本美術が特に好みです!(Twitter:@karub_imalive)
Editor | 静居 絵里菜
OBIKAKE編集部所属。楽しくやっています。